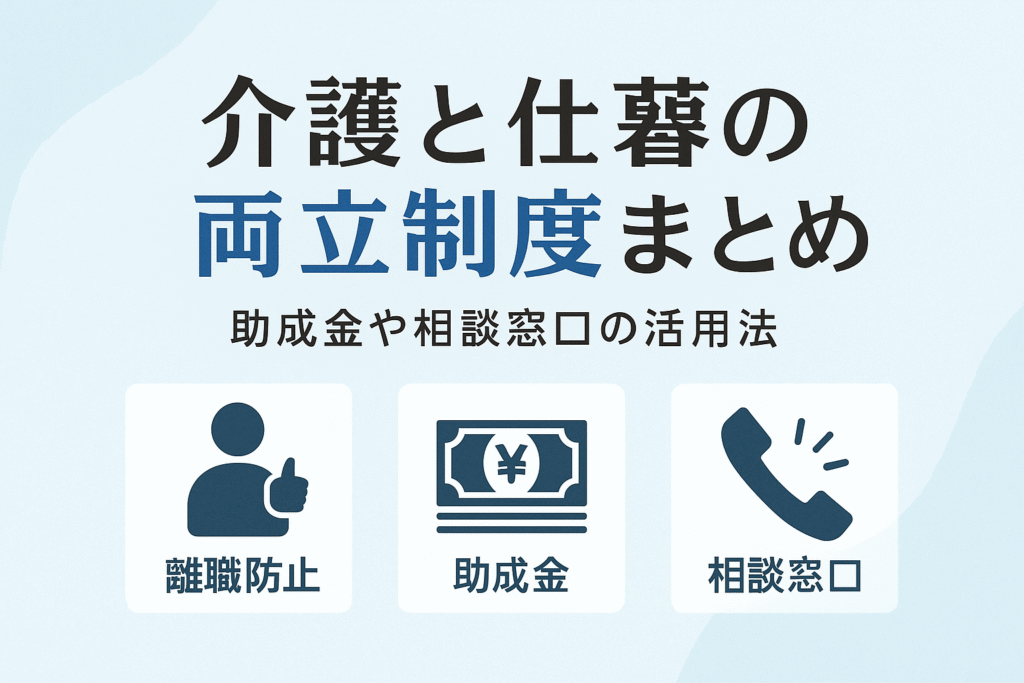「仕事と介護の両立は難しい…」そう感じていませんか?現在、日本の【介護離職者は年間約10万人】にのぼり、働きながら親の介護を続ける人の【約3人に1人】が「両立がきつい」「先が見えない」という不安やストレスを抱えています。特に40代・50代のビジネスパーソンは、突然の介護と日常業務の板挟みに直面し、【経済的損失や心身の不調を経験する人が急増】しています。
実際、2024年の厚生労働省統計でも、介護に伴う離職が企業の人材不足や家計への影響として深刻化しつつあります。さらに2025年からは法改正により、企業側にも新たな両立支援義務が加わるため、今まで放置してきた“仕事と介護の調整”はこれまで以上に重要になっています。
「一体どうすれば無理なく両立できるのか」「利用できる制度や支援は何があるのか」という疑問を抱えている方も多いはずです。本記事では【最新の法制度・助成金・成功事例】をわかりやすく解説し、あなたが“今”取れる具体的な選択肢・解決策を提示します。
難しそうと感じても大丈夫です。読み進めることで、「後悔しない両立のコツ」と、「あなたの家庭やキャリアに最適な支援」も見つけられます。どうぞ安心して次章へお進みください。
介護と仕事を両立する現状と社会的課題
介護離職の実態と労働力減少問題 – 高齢化社会における両立の困難さと経済的影響
日本では高齢化の進行により、働きながら家族の介護を担う人が増えています。近年では30代から50代の働き盛り世代が、親の介護で仕事との両立に悩むケースが多く見られます。介護を理由に離職する人の数は年間10万人超とも言われ、その影響は個人だけでなく企業や社会全体にも広がっています。
下記のテーブルは主な両立困難の要因をまとめたものです。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 時間的制約 | 仕事と介護のスケジュール調整が難しい |
| 経済的負担 | 収入減少や介護費用の増大 |
| 精神的負担 | 慢性的なストレスや不安、孤立感 |
両立ができずに仕事を辞めると家計が悪化し、将来的な社会保障費の増加や労働力不足につながる懸念も強まっています。
介護や仕事両立がきつい・できない悩みの共通点と心理的負担 – 介護負担によるストレスや疲労の実例と傾向分析
家族の介護と仕事を両立できない、両立がきついと感じる悩みは年齢や職種を問わず多くの人に共通します。大きなストレスや疲労、時間や心身の余裕のなさが理由となり、「仕事に集中できない」「心が限界」「人生に希望が持てない」といった葛藤を抱える人も少なくありません。
このような悩みには以下の傾向があります。
-
相談相手がいないことで孤独感が強くなりやすい
-
休暇取得が難しい職場環境では、心身ともに疲弊しやすい
-
子育てと介護のダブルケア状態になり、特にメンタル面の負担が大きくなる
強いストレスや疲労感は、長引くほど仕事やプライベートの質を著しく下げてしまいます。適切な支援や相談を活用することが重要です。
2025年問題と育児・介護休業法の改正動向 – 最新の法律義務化と企業への影響
2025年には、団塊の世代が一斉に後期高齢者となることで社会全体の介護ニーズがさらに高まります。この「2025年問題」に対応するため、育児・介護休業法も段階的に改正が行われ、企業への両立支援義務が強化されています。
最新の法改正ポイントをまとめます。
| ポイント | 概要 |
|---|---|
| 介護休業の柔軟な取得 | 分割取得が可能になるなど取得しやすく改正 |
| 労働者への情報提供の義務化 | 企業は制度や支援内容を社員へ周知する必要がある |
| 職場環境の整備促進 | 介護両立支援制度の導入や研修実施 |
企業は両立支援を義務として対応する必要があり、働く人も制度の情報を知って活用することで、安心して介護と仕事を両立できる社会が求められています。
仕事と介護を両立させるための基礎知識と最新支援制度の全体像
仕事と介護の両立は、多くの働く世代にとって深刻な課題となっています。親や家族の介護を必要とする状況が突然訪れることは少なくありません。介護による離職やメンタル面での負担を防ぎ、仕事を続けながら家族を支援するためには、利用できる制度や支援策を把握しておくことが大切です。ここでは「介護 仕事 両立」を実現するために知っておきたい基礎知識や最新の支援制度、相談窓口の活用方法までを詳しく解説します。
介護休業制度・介護休暇制度の詳細解説 – 利用条件・期間・給付内容までのフロー
家族を介護しながら働く方のために法で定められた制度が存在します。最も代表的なのが「介護休業制度」と「介護休暇制度」です。
| 制度名 | 対象者 | 期間・取得方法 | 給付内容 |
|---|---|---|---|
| 介護休業制度 | 要介護状態の家族がいる従業員 | 1人につき通算93日、3回まで分割可 | 介護休業給付金(賃金の67%) |
| 介護休暇制度 | 介護が必要な家族がいる従業員 | 年5日(2人以上なら年10日)半日単位・時間単位の取得も可 | 無給(給与支払いは企業ごと) |
ポイント
-
対象家族は配偶者、子、親、祖父母、兄弟姉妹など範囲が広いです。
-
介護休業給付金は、雇用保険から支給されます。
-
申請には事前の書類提出と認定が必要です。
活用することで仕事と介護の両立が実現しやすくなります。取得のタイミングや要件は勤務先の人事部や厚生労働省の制度案内ページで詳しく確認しましょう。
仕事と介護を両立支援する助成金や国・自治体の補助制度 – 申請手続きと活用ポイント
仕事と介護の両立を積極的に支援するため、国や自治体はさまざまな助成金や補助制度を用意しています。企業も活用できるものが多く、職場環境の整備や介護両立支援を推進しています。
| 主な制度名 | 内容 | 申請先 |
|---|---|---|
| 仕事と介護の両立支援助成金 | 両立支援の制度導入や介護休業取得を促した企業への助成 | ハローワーク・労働局 |
| 介護両立支援制度推進事業 | 従業員の相談や対応体制整備など企業への支援 | 地方自治体 |
| 介護サービス利用補助 | 事業所や自治体が設ける訪問介護・デイサービス等の利用補助 | 市区町村 |
申請手続きのポイント
-
企業の人事担当や労務担当と事前に相談し、必要書類や申請時期を確認しましょう。
-
個人が利用できる在宅ワークなども検討し、負担の軽減につなげる事が可能です。
-
国や自治体の公式サイトで毎年条件や内容が更新されているため、最新情報の確認が重要です。
補助を賢く活用することで、介護状態に直面しても仕事を辞めずに対応しやすくなります。
相談窓口・公的機関のサポート体制 – 相談内容ごとの連絡先と利用方法
介護と仕事の両立に悩んだら、適切な窓口に相談し早めに対策を取ることが大事です。国や自治体、企業内の担当部署では多様な支援体制が整っています。
| 相談窓口 | 対応内容 | 連絡先例 |
|---|---|---|
| 地域包括支援センター | 介護サービスの紹介、手続き支援 | 各市区町村の福祉課 |
| 介護と仕事の両立支援窓口 | 制度や働き方に関する相談全般 | 厚生労働省サイト、労働基準監督署 |
| 企業の人事・総務担当 | 就業規則、休業取得手続き、職場での相談対応 | 勤務先へ詳細確認 |
利用方法
-
自分や家族が介護状態にある場合、早めに公的機関や会社担当者へ相談することがポイントです。
-
どの窓口も無料で利用でき、制度の紹介から具体的な申請手続きまでサポートしています。
-
日々の不安や悩みも遠慮せず共有し、状況に応じたサービスを案内してもらいましょう。
仕事と介護の両立は一人で抱えこまず、信頼できる相談窓口やサポート体制を早めに活用することが安心して働き続けるコツです。
仕事と介護の両立に悩む人に向けた具体的な対処法と工夫
介護や仕事を両立するのが無理・できないと感じたときの心構えと実践策 – 自己管理と他者支援の活用
介護と仕事の両立が困難と感じたときは、まず自分の心身の状態をしっかり把握することが大切です。仕事や介護の負担を一人で抱え込まず、信頼できる家族や同僚、専門機関に相談することも有効です。以下のような実践策が役立ちます。
-
体調と感情の自己チェックを習慣化する
-
家族間で分担できることは話し合い、協力する
-
同じ立場の人の話や経験を聞いて安心感を得る
心が折れそうな時や「自分は両立できない」と感じても、こうした周囲の支援や自分自身での対策を組み合わせて状況改善を目指しましょう。
両立がきつい時に使える休暇や制度・外部サービスの活用例
国や地方自治体では仕事と介護を両立する人向けの支援制度が多数用意されています。活用できる休暇や外部サービスを把握すると負担を軽減できます。
| 制度・サービス名 | 内容 | 申請先・対象 |
|---|---|---|
| 介護休業制度 | 家族の介護が必要な時、一定期間仕事を休める | 勤務先 |
| 介護休暇制度 | 年次有給休暇とは別に短期間の休暇を取得できる | 勤務先 |
| 介護両立支援制度 | 相談窓口や支援金、時短勤務など様々な制度がある | 各都道府県・市区町村 |
| 介護保険サービス | デイサービス、訪問介護、ショートステイなどを利用可 | 自治体・ケアマネジャー |
これらを積極的に利用し、自分の働き方や生活に合ったサポートを選ぶことが重要です。申請や相談をためらわず、専門機関に早めに問い合わせてください。
相談サービスやオンラインコミュニティの利用で孤独感を減らす方法
両立生活では孤独や不安を感じやすくなります。その負担を和らげるためにも、各種相談窓口やオンラインのコミュニティ・掲示板を活用することがおすすめです。
-
地域包括支援センターの相談窓口の利用
-
オンラインの介護経験者コミュニティで情報交換
-
職場のメンタルヘルス相談や外部カウンセリングサービスの活用
これらを使うことで、「自分だけが悩んでいるわけではない」と実感できます。気軽な一歩から悩みを共有し、前を向ける環境づくりを心がけてみてください。
親の介護をしながら仕事を続けるためのケーススタディ集
親の介護をしながらできる仕事選びのポイントと職種紹介 – 在宅勤務・時短勤務可能な仕事
親の介護と仕事の両立を目指す方には、柔軟な働き方や在宅勤務ができる仕事が支持されています。介護しながら働くには、自宅での作業や時短勤務を積極的に活用できる職種を選ぶことがポイントです。IT関連(事務・WEBデザイン・プログラミング)、オンラインカスタマーサポート、データ入力などは、比較的自宅でも働きやすい職種として人気です。特に、フレックスタイム制や時短勤務が認められている企業を選ぶことで、介護と仕事のバランスを整えやすくなります。
| 分類 | 具体的な職種 | 特徴 |
|---|---|---|
| 事務系 | データ入力、経理補助 | 定型作業が多く在宅勤務可能 |
| IT系 | Webデザイナー、プログラマー | PC1台で業務可能、成果物で評価 |
| サポート系 | オンラインカスタマーサポート | シフト調整や短時間勤務がしやすい |
求人情報では「介護両立支援あり」「在宅勤務OK」などの条件も確認しましょう。
親の介護で仕事ができなくなった場合の支援と制度活用法
介護が急に必要になり仕事の継続が困難になった場合でも、介護休業制度や、公的支援を活用すれば負担を減らせます。介護休業法により、一定期間雇用を継続した従業員は通算93日まで介護休業の取得が認められています。また、介護休暇や時短勤務も選択可能です。職場に相談しにくい場合でも、地域の介護両立相談窓口を利用することで適切なアドバイスや支援につながります。
さらに、職場によっては介護支援制度や助成金制度を設けている企業も増えています。金銭的負担や不安を軽減させるために、働く人向けの給付金やサービス、地域包括支援センターのサポートを積極的に調べてみてください。
| 支援策 | 内容 | 申請窓口 |
|---|---|---|
| 介護休業制度 | 93日まで休業可能 | 勤務先人事部または労務管理担当 |
| 介護休暇・時短勤務 | 時間単位の有給利用も可 | 勤務先 |
| 両立支援助成金 | 介護休業取得社員向け | ハローワークなど行政機関 |
| 地域介護相談 | ケアプラン作成や相談 | 地域包括支援センター |
子育てと介護、仕事の三重両立を支える実例と工夫 – ダブルケア世代への具体的支援策
子育てと親の介護、そして仕事という三重の負担に直面する「ダブルケア世代」は増加傾向にあります。このような状況では、時間管理の工夫と外部サービスの積極的活用が鍵となります。家族で役割分担を行い、必要に応じてデイサービスや訪問介護などを利用しましょう。特に、同世代の体験談や企業の両立支援事例に学ぶことで新しい解決策が見つかります。
-
家族内でのタスク分担を明確化
-
病院や介護施設の送迎時間に合わせて勤務時間の調整
-
ケアマネジャーや地域支援サービスを活用
-
職場との定期的な面談で現状報告と配慮要請
地域によってはダブルケア対象の相談窓口や情報提供セミナーも開催されているため、不安を抱えずにまずは情報収集から始めることが大切です。日々の負担を一人で抱え込まず、頼れる仕組みと周囲の協力を得ながら、安心して働き続けられる環境を整えましょう。
介護職・福祉職における子育てや育児との両立の現状と対策
介護職の働き方改革と育児を両立するための成功事例
介護の仕事と育児の両立は、多くの人が抱える切実な課題です。時間的な制約や精神的な負担が大きく、「両立できない」「きつい」と悩む声も増えています。しかし、最近では働き方改革の推進により、育児と介護の両立がしやすい職場づくりが加速しています。
例えば、フレックスタイムや時短勤務、希望休の取得がしやすい環境を整えた施設では、育児中のスタッフの定着率が大幅に向上。下記の成功事例が注目されています。
| 取り組み内容 | 効果 |
|---|---|
| 時短勤務制度の導入 | 育児と仕事のスケジュール調整が容易に |
| シフトの柔軟化 | 保育園送迎と両立しやすい |
| テレワーク試験導入 | 家事・育児と両立できる時間活用が可能 |
| 育児休業後の復職支援 | 定着率向上・離職率低下 |
家庭や子どもの状況に合わせて勤務時間を調整できることが、両立のポイントです。
ケアマネ・社会福祉士など専門職の両立支援と就労環境
介護現場では、ケアマネジャーや社会福祉士など専門職の両立支援が重要視されるようになっています。厚生労働省の方針を受け、多くの事業所が両立支援制度を積極的に整備しています。
下記のリストは、専門職向けに拡充されている主な支援策です。
-
休業・休暇取得の促進
-
研修・スキルアップ機会の確保
-
個別面談による就業計画の見直し
-
業務分担の最適化
このように、支援制度と職場の理解が進むことで、「子育て中でもキャリアを継続できる」「働きながら資格取得を目指せる」と感じる人が増加しています。相談窓口や専用サイトを活用することで、現役の専門職でも両立の道が広がります。
介護業界での転職・就労支援情報と両立重視の企業比較
介護職として働く人の中には、親の介護や育児と仕事をどう両立するか悩み、転職や職種変更を検討するケースも多く見られます。近年は両立支援に力を入れる企業や事業所が増加し、働きやすい職場選びの要素となっています。
下記のポイントを比較し、自分に合った職場を探すことが重要です。
| チェックポイント | 両立重視企業A | 一般事業所B |
|---|---|---|
| 時短勤務制度の有無 | あり | なし |
| 介護・育児休暇の取得実績 | 高い | 低い |
| 在宅・リモートワーク対応 | 柔軟 | 未対応 |
| 復職プログラム | 充実 | 制度化なし |
両立支援に積極的な企業へ転職することで、家庭の事情や成長段階に合わせた働き方を実現できます。情報収集の際は「介護 仕事 両立支援」「両立できない 相談」といったサジェストを活用し、複数の求人サイトや自治体の就労支援窓口も比較すると安心です。
法改正による事業主の義務と対応すべき具体的施策
2025年改正育児・介護休業法の概要と事業主義務項目
近日施行される2025年の育児・介護休業法改正は、事業主に対する両立支援の義務がいっそう強化される内容となっています。特に、介護と仕事を両立する従業員支援の具体策が求められています。主な改正ポイントは下記の通りです。
| 項目 | 変更内容 | 事業主の具体的義務 |
|---|---|---|
| 両立支援制度の導入 | 介護休業・休暇の取得促進 | 制度の社内規定化と従業員への明示 |
| 制度周知・意見聴取 | 定期的・明確な周知義務 | 相談窓口設置・従業員意見聴取の実施 |
| 職場復帰支援 | 休業後の復帰プログラム構築 | 復帰時の業務配慮・相談体制の強化 |
従業員が安心して介護と仕事を両立できる環境を整えることは、離職防止や企業価値向上にも繋がります。最新の法改正に合わせて、社内制度や環境整備を見直していくことが不可欠です。
企業が整備すべき内製支援制度と効果的な周知方法
多様な支援制度の導入と従業員への周知が、両立支援において極めて重要です。以下のような制度を整備することで、従業員の「仕事と介護の両立」を現実的にサポートできます。
-
介護休業・休暇制度の柔軟化
-
時短勤務やテレワーク導入
-
介護に関する相談窓口の設置
-
介護費用助成や情報提供セミナーの開催
効果的な周知方法としては、定期的な社内研修やガイドブック配布、イントラネットでの専用ページ設置などがあります。社内周知の徹底が利用率向上の鍵となります。
仕事と介護の両立支援制度を活用していることを社内外に発信することで、従業員の安心感が高まります。
管理職・人事が実践すべき両立支援の具体的取組み事例
管理職や人事部門が積極的に取り組むことで、職場全体に「介護と仕事の両立支援」の文化が浸透します。代表的な事例は以下のとおりです。
-
定期的な両立支援研修の実施
-
個別事情ヒアリングと業務調整
-
介護両立支援制度の利用促進キャンペーン
-
復職者のフォローアップ面談とメンタルサポート
これらの施策を実施することで、従業員は介護と仕事の両立に対する不安を大幅に和らげることができます。加えて、同じ悩みを持つ従業員同士をつなぐ交流機会を設けることも、多くの企業で効果が出ている取り組みの一つです。
従業員の声を反映しながら、柔軟かつ実践的な支援を続けることが企業としての持続的成長の要となります。
介護と仕事の両立支援サービスと制度の比較分析と活用術
公的サービスと民間サービスの特徴・メリット・デメリット比較
介護と仕事の両立を支援するためには、公的サービスと民間サービスを正しく理解し、適切に選択することが重要です。以下のテーブルでそれぞれの特徴を整理しました。
| サービス種別 | 主な内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 公的サービス | 介護保険(訪問介護・デイサービスなど) 介護休業・介護休暇制度 | 費用負担が少ない 申請すれば全国共通で利用可能 制度上の安心感 | 利用までに手続きが多い 柔軟なサービス対応はやや限定的 |
| 民間サービス | 家事代行サービス 民間介護事業者による訪問・送迎 | サービス内容が多様・柔軟 緊急時でも手配しやすい | コストがかかる 事業者によって質に差がある |
公的な介護両立支援制度は、介護休業法に基づき職場での休業・短時間勤務などが義務化されており、多くの従業員が申請可能です。一方、民間サービスは日常の細かなニーズに柔軟対応できる点が強みですが、料金や事業者選定には注意が必要です。両立がきつい、無理だと感じた際は、どちらか一方に偏らず状況に応じた併用も効果的です。
利用者満足度・実績データからみる効果的な使い分け
公的サービスの利用者の多くは、費用負担の軽減や制度の安心感から高い満足度を示しています。一方、民間サービスは急な対応や個別性の高い支援が好評です。利用者から実際に寄せられる声をもとに、どの場面でどちらを使い分けるとよいかを整理しました。
効果的な使い分けのポイント
- 日常的なケアや定期的なサポートには公的サービス
- 突然のトラブルや24時間対応・細やかなニーズには民間サービス
- 介護休業や短時間勤務など職場制度も併用
実績では、家族の負担感が減少したという報告が多く、必要時は短期間でも民間サービスと公的支援を組み合わせて利用することで精神的余裕が生まれやすくなります。
利用者体験談に基づく現場の声とサービス選択のコツ
実際に介護と仕事の両立をしている方々の体験からは、現場ならではの悩みや工夫が浮き彫りになります。
現場の声(体験例)
-
「介護休業を使って公的サービスの手配に集中できた」
-
「親の認知症が進行し夜間も目が離せなくなったが、民間の夜間ヘルパーで安心できた」
-
「職場の理解を得て働き方を調整、両立支援制度と民間サービスを併用し乗り越えた」
サービス選択のコツ
-
利用できる公的制度や助成金を早めに把握し、必要に応じて相談窓口を活用
-
無理をせず、きついと感じた段階で家族だけで抱え込まず外部サービスを検討
-
職場の両立支援担当と面談し、両立の希望や状況を共有、社内制度も最大限利用
このような体験談を参考にすると、精神的負担が大きい場合や両立に疲れたと感じた時は、家族や専門家のアドバイスも取り入れながら柔軟なサービス選択が重要だということがわかります。
よくある質問と専門家からのアドバイス(Q&A形式で展開)
仕事と介護を両立するときに抱えがちな疑問・課題とその回答
介護と仕事を両立する方からは「両立支援制度の利用方法」「会社への相談の仕方」「精神的・身体的な負担軽減策」など多くの疑問や悩みが寄せられます。よくある質問とその回答を下記にまとめました。
| 困りごと | 回答 |
|---|---|
| 家族の介護が始まり、仕事も辞めたくないが両立が不安です | まずは勤務先の両立支援制度をチェックし、上司や人事担当に早めに相談しましょう。介護休業や時短勤務が利用できる場合があります。 |
| 介護と仕事の両立はどこに相談できますか? | 会社の人事だけでなく、自治体や地域包括支援センター、窓口を活用できます。専門家への相談で最適な支援や情報も得られます。 |
| 両立がきつい場合、どうやってストレスを減らせますか? | 一人で抱え込まずに、第三者のサポートや在宅サービス、デイサービスなども利用しましょう。また「きつい」と感じたらメンタルケアも大切です。 |
自宅介護と勤務継続の具体的な調整方法
自宅で家族を介護しながら働く場合は、業務時間や働き方の見直しが重要です。柔軟な働き方を選択することで、職場への復帰や仕事の継続を実現しやすくなります。
具体的な調整ポイント:
-
勤務時間の短縮やシフト変更: 法に基づく時短勤務や時差出勤制度を申請できる場合があります。
-
テレワークの積極的活用: 許可が得られる場合は、在宅ワークも選択肢です。出社負担軽減につながります。
-
業務内容や担当の再調整: 上司と話し合い、負担の少ない業務や柔軟な業務割り当てを希望しましょう。
-
家族や周囲の協力依頼: 家族で協力体制を整え、必要なら外部サービスを組み合わせましょう。
会社の「介護両立支援制度」や地域の相談窓口を事前に確認しておくと、突発的な対応もしやすくなります。
介護休業取得時の注意点と制度活用のポイント
介護休業を取得する際は手続きや条件に注意が必要です。下記の表を参照し、制度を有効に活用しましょう。
| 項目 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 対象家族 | 配偶者、両親、子、配偶者の父母など | 継続的な介護を要する場合に限られます |
| 取得期間 | 最大93日(分割取得可) | 回数や期間は就業規則も確認 |
| 申請方法 | 会社指定の書類で申請 | 早めの相談・申請がポイント |
| 金銭面 | 雇用保険「介護休業給付金」あり | 金額や支給要件の事前確認が必要 |
ポイントとしては、
-
制度利用は会社への早めの相談が重要
-
給付金や助成金は条件を満たす場合のみ支給対象
-
家族だけで抱えず、社会資源・制度を積極的に利用すること
制度やサービスを上手に使うことで、介護と仕事の両立が現実的になります。悩んだときは速やかに専門家や相談窓口へご相談ください。
未来を見据えた介護と仕事の両立のための準備と心得
効率的な情報収集の方法と信頼できる情報源
介護と仕事を両立するためには、信頼できる情報収集が大きなポイントとなります。正確な制度や支援の内容を知るために、下記の情報源を活用すると効率的です。
| 情報源 | 主な内容 |
|---|---|
| 厚生労働省 | 介護保険や両立支援制度の最新情報 |
| 市区町村の窓口 | 地域独自のサービスや相談窓口案内 |
| 企業の人事部門 | 勤務先で利用できる両立支援制度 |
| 介護事業所 | 実際のサービス利用方法やケアマネ相談 |
多くの人が必要な情報にたどり着くのに苦労していますが、制度の変更や新しい支援策は公式機関を定期的に確認しましょう。職場に両立支援担当がいる場合は積極的に相談し、家族とも状況を共有することも重要です。
今後増加するリモートワーク・柔軟勤務を活用した両立促進
テクノロジーの進化とともに、柔軟な働き方を選択できる企業が増え、介護と仕事の両立がしやすくなっています。リモートワークや時差出勤、フレックスタイム制度などの利用が課題解決の大きな助けになります。
- リモートワーク
自宅で仕事をすることで、急な対応にも柔軟に動けます。
- 時差出勤・フレックス制度
通院や介護サービスの時間帯に合わせて勤務調整が可能です。
- 職務の見直しや分担
負担を軽減しつつ、仕事の継続がしやすくなります。
企業によって利用できる仕組みが異なるため、自身の勤務先の制度を詳しく確認しましょう。希望する働き方がある場合は早めに上司や人事に相談するのが大切です。
介護と仕事の両立で心身の健康維持を目指す生活習慣とセルフケア
介護と仕事の両立は大きな負担となるため、心身の健康を守るケアが欠かせません。無理をせず、適切なセルフケアを継続しましょう。
-
十分な休息と睡眠の確保
-
バランスの良い食事を摂る
-
可能な範囲で身体を動かす(散歩やストレッチなど)
-
信頼できる人や専門家への相談
-
介護サービスの活用で自分の時間を作る
ストレスが限界にならないよう、自身のメンタル状況を意識することが重要です。時には介護疲れチェックリストなどを用いて、自分の状態を確認するのもおすすめです。必要に応じて専門機関に相談することで、無理のない両立を続けることができます。