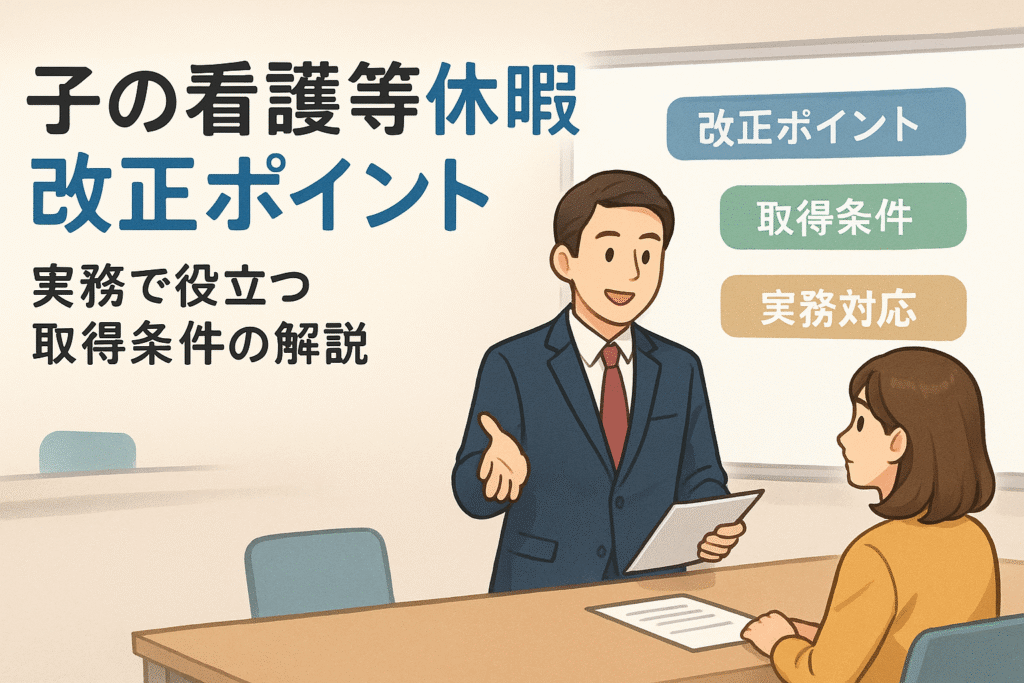小さなお子さんの体調不良や急なトラブルで、仕事と育児の両立に悩んでいませんか?2025年4月の法改正により、「子の看護等休暇」が大きく見直されました。これまで小学校就学前児童が対象だった取得範囲が「小学校3年生修了まで」に広がり、年間5日(子が2人以上の場合は10日)の休暇取得が可能となります。さらに、感染症による学級閉鎖や入学式・運動会など、休暇を取得できる理由も拡充されました。
「毎年2人に1人が仕事を休まざるを得ない」と言われる保護者の困りごとに対し、今ではより幅広い「育児と働き方の両立支援」が実現しやすい環境が整いつつあります。また、非常勤や短時間勤務など多様な働き方でも取得対象となるケースが増えたことで、実際の現場負担軽減にもつながっています。厚生労働省の最新調査によれば、取得率は年々上昇し、2024年度には民間・公務員あわせて【約60%】以上が活用しています。
「手続きや証明書の用意が面倒そう…」「どこまで取得できる?」といった疑問もこの記事ですべて解消。新制度のポイントと実際の活用例まで、見落としがちな注意点も含めて徹底解説しています。この先を読むことで、あなたとご家族の「万が一」に確実に備える知識が手に入ります。
子の看護等休暇とは―2025年改正でどう変わる?基礎知識と最新制度概要
子の看護等休暇の意味と社会的背景 – 育児支援制度としての位置付けと取得意義をわかりやすく解説
子の看護等休暇は、保護者が小学校3年生までの児童を看護または健全な成長のために取得できる特別な休暇です。家庭と仕事を両立するための支援策の一つとして注目され、感染症やけがによる看護だけでなく、運動会や授業参観など学校行事への参加も対象に含まれます。この制度は子育て世代の労働意欲を高め、多様な働き方を実現するためにも大きな役割を果たします。
育児介護休業法における子の看護等休暇の法的な位置づけと対象者
子の看護等休暇は、育児介護休業法で規定されている育児支援休暇の一種です。対象となるのは、小学校3年生修了前までの子どもを養育する労働者で、正社員だけでなくパートや派遣職員、公務員も含まれます。取得日数は子ども1人につき年間5日まで、2人以上なら10日まで申請可能です。また時間単位での取得や、学校行事・感染症による臨時休校など多様な事由に対応しています。
制度改正の要点と名称変更の背景 – 子の看護休暇から「等」追加の意味と改正ポイント全体像を整理
2025年の法改正では「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」へと名称が変わり、支援内容がさらに拡充されました。主な改正点は以下の通りです。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 対象:小学校就学前まで | 対象:小学校3年生修了まで |
| 理由:病気やけが等の看護 | 理由:感染症流行時の休校、運動会・授業参観等の学校行事参加も対象 |
| 一部例外労働者は対象外 | 包括的に対象労働者を拡大し除外規定を見直し |
このように、より広範囲の子育て・養育支援を目的に制度が刷新されました。
改正前後の比較で理解する制度改正の核心
改正により、小学生の保護者も学校行事参加のために休暇を取得しやすくなりました。下記のリストでポイントを整理します。
-
子どもの「感染症による学級閉鎖」や「入学式」「参観日」「卒園式」なども休暇取得対象に
-
公務員も民間同様に取得可能
-
時間単位での取得が義務化し、柔軟に運用しやすい
-
申請書による手続きを経て、原則無給
これにより、「看護休暇が無給で意味がない」「対象が狭い」といった従来の課題に大きな改善が生まれます。
改正の社会的インパクト – 労働環境や家庭への具体的メリットと課題
今回の改正には多くのメリットがあります。子育て世代の労働者は、仕事と家庭をより両立しやすくなり、企業側も多様な人材確保や定着に寄与できます。また、育児介護休業規程例などを整備することは、働き方改革の推進にもつながります。一方、無給での運用が中心となるため、経済的な負担を不安視する声や、「有給休暇とどう使い分けるか」といった実務面の課題も残されています。今後は制度の周知と職場での柔軟な運用がますます求められます。
子の看護等休暇の対象者や年齢範囲・取得条件の詳細
小学校3年生修了までの対象拡大の具体的意味 – 就学猶予児や複数子ども対応例も含めた詳細説明
子の看護等休暇は、育児介護休業法の改正により、対象となる子どもの年齢が「小学校3年生修了まで」に拡大されました。これにより、従来は主に小学校入学前までだった対象範囲が大きく広がり、より多くの家庭で実用性が高まります。小学校に就学猶予がある場合も年齢ではなく「修了」までが原則となります。また、兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの子どもについて別々に日数を取得できます。
下記の表で対象児童や取得可能な日数のポイントを整理します。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対象児童 | 小学校3年生修了までの子供 |
| 就学猶予児の扱い | 就学猶予後も3年修了までが対象 |
| 取得可能日数 | 子1人につき年5日(2人以上は年10日以内) |
| 単位 | 1日・半日・時間単位(会社規程で対応可) |
主な取得理由として、インフルエンザ等の感染症・学級閉鎖・入学式や運動会・授業参観など学校行事への対応も明記されました。これによって、看護や通院だけでなく行事参加や急な対応も正式に認められています。
勤務形態や労使協定による対象除外規定の見直しによる実務上の影響解説
今回の改正では、パートや非正規を含む幅広い雇用形態の労働者も取得しやすくなりました。従来、「短時間勤務」や「6ヶ月未満の勤続」の場合は会社と労使協定を結ぶことで休暇対象から除外できましたが、見直しにより対象外範囲が大幅に縮小。また、就業規則や育児介護休業規程の見直しが各社に求められています。
【会社の実務で押さえるべき主な変更点】
-
勤続6ヶ月未満でも基本的に取得可能になった
-
除外対象は日雇い労働者などに限定
-
労使協定の締結がない場合も取得できる
-
規程例・申請書の見直しや配布が必要
勤務形態ごとの権利が明快になり、「休暇が使えない」「拒否された」といったトラブルも減少する見込みです。
公務員や非常勤労働者の取得要件と違い – 働き方別の権利拡大と留意点
子の看護等休暇は民間企業の労働者だけでなく、公務員や非常勤職員にも広く適用されます。地方公務員や国家公務員にも育児介護休業法の枠組みが準用され、各自治体でも制度整備が進んでいます。非常勤の場合は雇用期間や勤務日数で休暇取得条件が付くこともありますが、原則として同様の権利が認められます。
【働き方別・主な確認事項】
-
公務員は制度内容や日数が条例・規則等で定められ、学校行事や看護が明記
-
非常勤講師やパートなど短時間労働者も、賃金計算や無給・有給の判断が求められる
-
公務員の場合、運用基準や対象事由が都道府県・所属自治体で異なるため、所属先の人事担当課に確認
社会全体で育児と仕事の両立支援が進み、どの働き方でも公平な取得機会の確保が重要とされています。
子の看護等休暇の取得理由や使えるシーンの具体例
従来からの看護理由以外に加わった取得理由 – 感染症学級閉鎖、入学式・卒園式・運動会・授業参観など詳細列挙
子の看護等休暇は、従来の「子どもの傷病や看護」という理由に加え、さらなる多様な理由が新たに認められています。2025年の育児介護休業法改正により、感染症流行による学級閉鎖や入学式・卒園式、運動会、授業参観など学校行事への参加も取得理由として追加されました。また、学校からの呼び出し対応、PCR検査への付き添い、インフルエンザなど感染症流行時の看病も該当します。下記は代表的な取得理由の一覧です。
| 取得理由 | 詳細例 |
|---|---|
| 子どもの病気・けが | 発熱・インフルエンザ・骨折・通院・入院 |
| 感染症流行による学級閉鎖 | コロナ・インフルエンザ等の学級・学年閉鎖 |
| 学校行事 | 入学式・卒業式・運動会・授業参観・参観日・修学旅行説明会 |
| 学校からの呼び出し | 発熱やけがによる途中呼び出し・緊急時の対応 |
| 各種付き添い業務 | ワクチン接種・PCR検査・健康診断の付き添い |
このように、単なる病気やけがだけでなく「子どもを取り巻く幅広い事由」が対象になっています。
各取得理由の注意点や証明資料の要否
子の看護等休暇を取得する際には、理由によって注意すべき点や証明資料の提出が必要になるケースもあります。たとえば学級閉鎖での利用では、学校からの休校通知文書や、お知らせメール画面の写しが証明資料として利用されることが多いです。入学式や卒園式など学校行事の場合は、学校行事予定が記載されたプリントや案内状が有効です。傷病による取得であれば、診断書や通院記録は基本的に求められませんが、会社ごとに書類規程がある場合もあります。
実際の申請手続きには以下の点に注意しましょう。
-
利用理由を明確にし、必要に応じて資料を提出する
-
就業規則や子の看護等休暇規程例を必ず確認する
-
無給・有給の区別は企業ごとの規定によって異なるため給与明細や人事へ確認する
信頼される取得のためには、正当な理由の記載と証拠書類の備えが重要です。
多様な家庭事情に対応する実例紹介 – 現場声も交えながら利用イメージを具体化
子の看護等休暇は、実際にさまざまな家庭事情や子どもの成長段階に応じて利用されています。たとえば、小学校1年生の終わりに突然のインフルエンザ学級閉鎖が発生した際、母親が時間単位で看護等休暇を活用し早めに帰宅、家庭で感染対策を徹底できたケースもあります。別の例では、父親が入学式に出席するために半日分の看護等休暇を利用し、普段は仕事で参加できない行事にも参加できたといった声もあります。
・小学生の授業参観や運動会の際、祖父母等が遠方で頼れない場合でも、労働者自身が申請し参加が可能に
・シングル家庭や共働き家庭が急な発熱時にも柔軟に取得しやすくなり、欠勤や有給休暇を優先せずとも子育てと就業の両立が実現
こうした多様な活用事例は、特に無給であっても「子どもの成長を見守る時間」を確保できる点で意義が大きいと実感されています。会社によっては申請書のフォーマットが整備されている場合もあるので、規程内容も併せて確認しましょう。
子の看護等休暇の取得単位・日数・賃金(有給・無給)に関する詳細解説
子の看護等休暇の時間単位取得の可否と義務規定 – 最新法令準拠ルールと実務例
子の看護等休暇は、一定の条件を満たす場合、時間単位での取得が可能です。法令では1日単位または半日単位の取得が基本ですが、就業規則や労使協定で定めれば1時間単位でも取得できるため、柔軟に対応できます。ただし、企業ごとに「時間単位の取得義務」があるわけではなく、会社の制度として定めて初めて適用となります。実際の運用では、申請時に希望する単位を選べるよう規程例を定める企業も増えており、保護者が子どもの急な発熱や短時間の行事参加にも利用しやすくなっています。時間単位取得を導入する場合は、労働時間管理や残業計算にも配慮が必要です。
労働時間管理や申請単位の工夫ポイント
時間単位での取得運用では、休暇時の始業・就業時刻管理が重要です。例えば、午前中のみ出勤して午後は休暇取得など、フレキシブルな働き方の実現が可能となります。申請書の運用例としては、「取得希望時刻」「理由」「対象となる子の学年や氏名」など、必要情報をあらかじめ明記する形式が推奨されています。システムや紙での一元管理による取得状況の正確な記録が長期間のトラブル予防につながるため、企業は運用基準と申請フローを明確にし、従業員にも積極的な啓発を行うことが大切です。
年間取得日数と子ども人数別の管理方法 – 配分の柔軟性を含む実務解説
子の看護等休暇は、対象となる小学校3年生終了までの子ども1人につき年間5日、2人以上であれば年間10日まで取得できます。以下の表の通り、日数には上限がありますが、子どもごとに配分を変えることも可能です。
| 対象となる子どもの人数 | 年間取得可能日数 |
|---|---|
| 1人 | 5日 |
| 2人以上 | 10日 |
取得日数の管理では、兄弟姉妹の体調不良や感染症の流行、学校行事(運動会、授業参観、入学式、卒園式など)に応じて、必要な日数を分配できる柔軟性があります。事業所は各従業員の取得状況を正確に管理し、年間を通じてバランスよく休暇を利用できるようサポートすることが求められています。
有給無給の扱いの実情と労使での運用差異 – メリット・デメリット客観的に整理
子の看護等休暇は原則として無給です。しかし、一部の企業や自治体では独自に有給扱いとする場合もあり、労働協約や就業規則で定められています。無給運用の場合、従業員の金銭的不安がデメリットとして挙げられ、活用率が伸び悩む原因となることもあります。一方で、有給とした場合は、育児や家庭の両立がしやすくなり、従業員満足度や職場定着率向上にも貢献します。以下に代表的な違いをまとめます。
| 項目 | 無給のケース | 有給のケース |
|---|---|---|
| 勤怠 | 欠勤扱いだが、法定休暇のため減点なし | 有給休暇分として給与支給 |
| 取得率 | 金銭的理由で取得控える場合も | 利用しやすくなる傾向 |
| 企業負担 | 賃金コスト抑えられるが従業員離職リスク増加 | 賃金負担増だが、制度活用・満足度向上 |
取得日数が足りない場合は年次有給休暇の利用が可能です。自社の運用ルールをしっかり確認しましょう。
有給休暇との優先順位と併用ルール
子の看護等休暇と年次有給休暇は併用が可能ですが、どちらを優先すべきかは企業の就業規則により異なります。多くの会社では、まず子の看護等休暇の枠を優先的に消化し、日数超過時のみ年次有給休暇を利用する運用としています。有給休暇は給与が支給されるため、無給になることを避けたい場合には、年次有給休暇の申請を選ぶ従業員もいます。両制度を上手に使い分けることで、家庭の負担と収入減少リスクを最小限に抑えやすくなります。利用前には自社の規程や制度概要、申請フローを十分に確認することが重要です。
子の看護等休暇の申請方法・必要書類・証明の具体的運用ガイド
子の看護等休暇の申請フロー解説 – 会社への申請手続き・口頭・書面提出の実例
子の看護等休暇を利用する際の申請は、職場の規定によって異なりますが、多くの場合、事前またはやむを得ない場合は事後に申請書や連絡が必要です。主な申請フローは以下の通りです。
- 休暇取得の意向を上司や人事担当者に伝える
- 必要書類(申請書など)を提出
- 承認後に休暇を取得、勤務管理簿などに記録
多くの企業では申請手段は書面とされていますが、急な発熱や感染症による学級閉鎖・保育園からの呼び出しなど緊急時は口頭・メールでも認められる場合があります。会社独自の申請書フォーマットや時間単位での取得申請(規程例に明記必須)にも注目しましょう。
申請書記入例とよくある書類不備の回避ポイント
申請書の記載例は下記のテーブルの通りです。手続きがスムーズになるよう、不備が発生しやすい項目に十分注意してください。
| 必要項目 | 記入ポイント |
|---|---|
| 申請者名 | 署名または社員番号と併記 |
| 取得希望日 | 日付または時間帯を明確に記入 |
| 対象となる子の氏名 | 複数の場合は全員記入 |
| 休暇の理由 | 発熱、運動会、授業参観など具体的に |
| 連絡先 | 休暇中の緊急連絡先も記載 |
ありがちな不備は「取得理由の不明瞭」「子どもの氏名の記入漏れ」「申請日と実際の取得日が異なる」などです。不備を防ぐために、会社の規程例やマニュアルを事前に必ず確認しましょう。
証明書類の種類・提出時の注意点 – 病院の診断書、学校の証明、保育園の連絡など具体例
子の看護等休暇の利用事由が認められるか、会社が証明を求めるケースでは以下の書類が活用されます。
-
病院の診断書や領収書(病名・通院日明記)
-
保育園・幼稚園からの緊急連絡メールや通知文
-
学校行事(運動会・授業参観・入学式など)の案内状やイベント告知
-
公務員の場合は証明様式が定められていることも
証明書類の提出タイミングは会社規程に従う必要があります。不正取得とならないよう、内容の整合確認や原本の保管にも注意が必要です。
労使協定締結時の評価・申請拒否対応の事例説明
子の看護等休暇の取得に関して、労使協定の内容に基づき一部労働者(例えば日雇い、特定の雇用形態など)が除外されている場合があります。ただし改正によって、取得を希望する全ての労働者への対応が厳格化しました。
申請拒否は「休暇事由が不適切」「必要書類が著しく不備」「業務に重大な支障が出る場合」などに限定されます。拒否理由や状況は書面で明確に伝え、不当拒否とならないように配慮が求められます。事業場の規模や業務内容による対応事例と、その解決策についても企業は社内規程やQ&Aで明示しておくことが重要です。
企業や労務担当者向け子の看護等休暇の社内規程と就業規則改定ポイント
就業規則・育児介護休業規程への規定例紹介 – 実際のモデルケースを基に解説
2025年4月の育児介護休業法改正では「子の看護等休暇」が大幅に拡充され、社内規程・就業規則の改定が必須となります。具体的には、対象となる子どもの範囲が小学校3年生修了までに拡大され、運動会や授業参観、入学式などの学校行事参加も取得事由として正式に認められるようになりました。このため、就業規則や育児介護休業規程の見直しでは、下記の点を条項に盛り込む必要があります。
主な記載例
| 規程内容 | 反映ポイント |
|---|---|
| 取得できる対象者 | 小学校3年修了までの子を養育する全労働者 |
| 年間取得可能日数 | 子1人につき年間5日・2人以上の場合は年間10日 |
| 取得理由例 | 感染症、運動会、授業参観、入学式、卒園式など |
| 取得単位 | 1日・半日・時間単位で取得可 |
| 賃金の取扱い | 無給/有給の明記(法律上は無給が原則) |
| 申請手続 | 事前に申請書提出。緊急時は事後報告も認める |
例文を参考に、自社の運用・労務管理体制に合わせて社内規程を調整してください。
反映すべき法改正点と改定時の注意事項
今回の法改正を規程へ反映する際には、対象範囲の拡大と取得事由の多様化を余さず盛り込むことが重要です。小学校3年生までの全児童・生徒、学校行事・各種感染症等を理由として明文化することで、取得拒否やトラブルの予防につながります。
改定時には以下の点に留意が必要です。
-
社員から「無給のため意味がない」との意見が出ることを踏まえ、有給化や会社独自の手当設定の可否も検討
-
公務員・非正規・パートにも対象を限定せず明示
-
所定労働時間が短縮またはシフト制の場合の時間単位取得の運用細則をわかりやすく記載
-
労使協定による除外規定も最新ルールへ必ずアップデート
社内説明資料も法令文のままではなく、表や具体例を交えてわかりやすくまとめることが大切です。
企業が準備すべき運用フローと周知の仕方 – 労務管理者目線の実務ガイド
法改正対応後、実際の運用をスムーズに行うためには社内フローの整備と徹底した情報周知が不可欠です。下記の流れで実務対応を進めましょう。
-
社内規程の改定通知(イントラ・朝礼・全社メールで案内)
-
取得申請書のフォーマット更新と配布(紙・電子データで提供)
-
具体的な申請手順と必要書類の周知(FAQやリーフレット用意)
-
取得事由・日数・時間単位取得の具体事例を提示し質問窓口を明確化
-
勤怠管理システムの設定変更や担当者研修の実施
運用ポイント例
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 申請受付 | 原則事前申請だが、急病等は事後も可能 |
| 承認フロー | 所属長→人事部門で迅速判断 |
| 勤怠管理 | 時間単位の場合も正確に記録 |
| 社内Q&A | 運動会や授業参観も対象、無給だが有給活用も可能 |
社員が安心して制度を使えるよう、可視化しやすい説明を徹底しましょう。規程例の提示や運用の実例を交えることで、現場での混乱や誤解を防げます。業務効率を損なわず、法令遵守と両立支援を実現する運用を心掛けてください。
子の看護等休暇の実務トラブルと対応策・利用促進方法
申請拒否・権利行使に関するトラブル事例 – 法的根拠と解決方針
子の看護等休暇は法律に基づく労働者の権利ですが、現場では申請を拒否されたり、取得事由について誤解が生じるケースが見られます。たとえば、運動会や授業参観など子どもの行事参加を理由に認められない、勤務シフト上の都合で休暇取得を断られるなどが典型例です。
法的には、事業主が子の看護等休暇の申出を一方的に拒否することはできません。下記のテーブルで典型的なトラブルと解決策をまとめます。
| トラブル例 | 法的根拠 | 対応策 |
|---|---|---|
| 休暇申請を会社が拒否 | 育児・介護休業法で権利保証 | 労働者本人が制度の説明文書を提示し、職場内で再確認 |
| 取得理由細部で認めない | 改正内容で行事参加も対象 | 対象行事を社内規程に明記して周知 |
| シフトや人手不足を理由に拒否 | 正当な理由にならない | 労務管理の再調整・代替人員の検討 |
問題が発生した際は冷静に法律や就業規則を根拠に対話を進めることが重要です。
非取得理由の理解不足や誤解を招くケース – 「無給だから意味ない」等の誤解検証
子の看護等休暇が利用されにくい要因のひとつに「無給だから意味がない」「休んだ分給与が減るなら欠勤と同じ」といった誤解があります。実際にはこの休暇は無給運用が主流ですが、制度自体は法律上しっかりと定められており、欠勤扱いとは異なります。
強調したいポイントは以下の通りです。
-
子の看護等休暇は無給が原則だが、欠勤扱いではない
-
就業規則や労使協定で有給化することも可能
-
有給休暇より申請理由が限定されるが、就業保障には効果がある
また、「公務員の場合」「会社規定によって違いがある」など職種や事業所ごとに運用の違いが生じるため、自身の就業規則を確認し、不明点は担当部署に相談することが大切です。
くり返し利用しやすい職場環境づくり – 事例紹介と改善策
子の看護等休暇を日常的に利用しやすい環境づくりは、職場の両立支援促進や人材定着に直結します。制度の定着に成功している職場では、下記のような取り組みが進んでいます。
-
制度利用者の実体験を社内報で共有
-
シフト見直しや業務分担の柔軟化
-
申請書のオンライン化など手続き簡略化
-
管理職向け研修や社内FAQの整備
これらの施策を導入することで、「申請しにくい」「職場に迷惑がかかる」といった心理的障壁が下がり、両立支援が根付いた事業所では取得率も年々向上しています。モデル規程や参考となる申請様式を導入し、継続的な情報発信を行うことが重要です。
関連制度との比較や連携と育児支援の未来展望
育児休業・介護休業等他制度との違いと連携 – 子の看護等休暇の役割を体系的に把握
子の看護等休暇は、育児休業や介護休業など類似制度との明確な違いと連携が重要です。例えば、育児休業は原則として子の出生から一定期間の長期休業に対応し、介護休業は家族の介護を目的としています。一方、子の看護等休暇は、短期間かつ突発的な子どもの病気や学校行事などに柔軟に対応できる制度です。特に2025年の法改正以降は小学校3年生修了までの子を対象とし、運動会や授業参観、入学式といった行事も取得理由に含まれるようになりました。以下の比較表を参考にしてください。
| 制度名 | 主な目的 | 対象範囲 | 取得できる理由例 | 取得単位 |
|---|---|---|---|---|
| 子の看護等休暇 | 子の看護や行事参加 | 小学校3年修了まで | 病気、感染症、行事 | 1日・時間単位 |
| 育児休業 | 出産・育児支援 | 原則1歳未満(延長あり) | 出産・育児 | 長期(連続日数) |
| 介護休業 | 家族の介護 | 家族(配偶者、親など) | 介護全般 | 長期/日単位 |
それぞれの制度の役割を理解し、状況に応じて使い分けることで、家族全体の働き方の柔軟性と支援が向上します。
最新の社会事情・法改正動向の抜粋と対応の必要性
社会全体で育児や家族ケアへの関心が高まる中、2025年施行の法改正は働く親の負担軽減と多様な支援体制の拡充を推進しています。感染症流行による学校の一斉休校や学級閉鎖、学習行事の増加など、現代ならではの子育て課題を制度が幅広くカバーするよう進化しています。今回の改正で、従来の取得事由に加えて入学式・卒園式・授業参観・運動会・感染症対応なども休暇取得の対象となりました。これにより、企業も規程例の見直しや周知徹底が求められています。職場の理解浸透と適切な手続き運用を進め、誰もが安心して利用できる体制整備が重要です。
公的データに基づく活用推進の現状と支援強化策
公的機関の調査によると、子の看護等休暇の取得率は依然として伸び悩む傾向にあります。理由として、申請手続きの煩雑さや無給であることの経済的な負担感が指摘されています。例えば、取得日数の上限は、子ども一人あたり年間5日まで(複数なら10日)で、時間単位取得も可能ですが、一部の事業所では有給化されていません。今後、取得を促進するには、下記のような取り組みが重要です。
-
申請書など手続き様式の統一・簡素化
-
無給から有給への移行や賃金補助策の導入
-
規程例やリーフレットなどによる周知強化
-
人事・労務担当者の研修充実
政府の支援策や、最新の厚労省ガイドラインに基づく運用を参考にすることで、利用者と事業所双方にとってメリットのある制度設計が求められています。