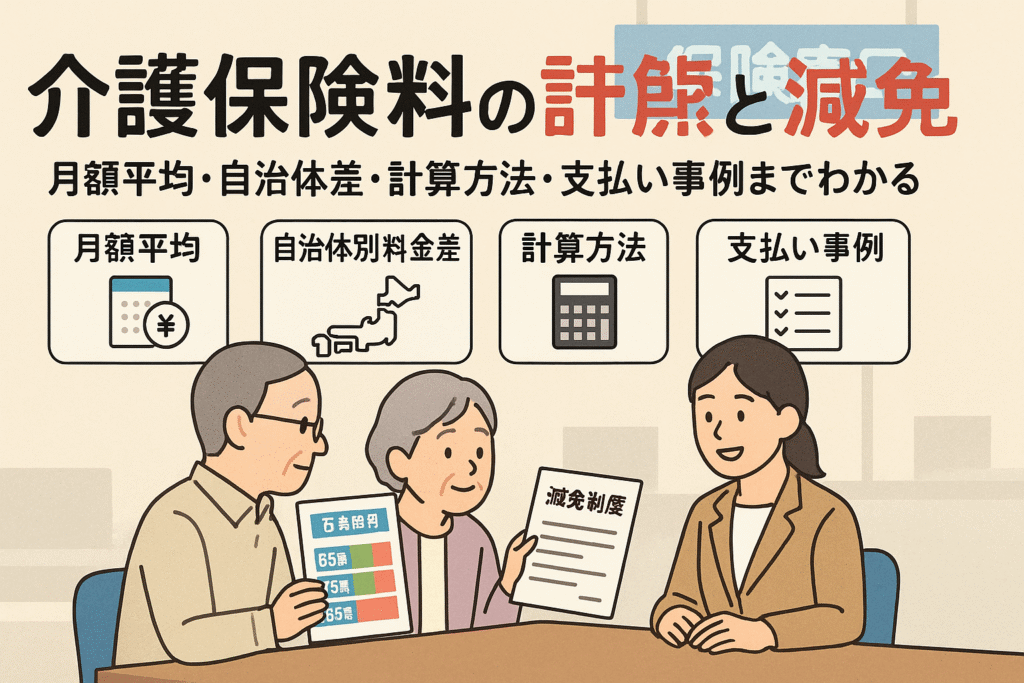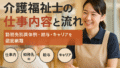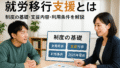「介護保険料って、毎月いくら支払えばいいの?」「地域によってこんなに違うなんて…」と、将来の負担に不安を感じていませんか。
介護保険料は【2024年度の全国平均で月額約6,225円】。しかし実際には、例えば大阪市では月7,486円、山口市なら5,568円と、自治体によって年間で約2万円もの差が生じています。しかも、40歳から義務化され、65歳を超えると年金から自動天引きになるなど、年齢や職業で支払い方法や金額も細かく変わるのが特徴です。
「知らなかった」では済まされない金額に後悔しないためにも、この記事では公的データや最新統計を用いて、月額の仕組みから地域別・年齢別の実態、軽減制度までわかりやすく解説。
今のうちに知っておけば、ムダな出費も安心の老後も自分で守れます。あなたの「今」に寄り添いながら、手取り早く必要な情報をまとめています。最後までお読みいただくことで、誰でも「納得」できる答えと安心が手に入ります。
介護保険料は月額の基本構造と対象者の理解
介護保険料は月額とは何か?制度の意義と概要 – 介護保険制度の目的と保険料の役割を解説
介護保険料の月額は、主に40歳以上の人が公的介護保険制度に参加するために毎月支払う金額です。この制度は、誰もが安心して老後の介護を受けられる社会を実現するために作られました。保険料は介護サービスの財源となり、要介護認定を受けた際に費用の一部として利用されます。月々の支払いは、年齢や所得、居住する自治体ごとに異なり、社会全体の連帯で支え合う仕組みを形成しています。
介護保険料は第1号被保険者・第2号被保険者の定義と対象範囲 – 40歳から始まる支払い義務の違いを明確に
介護保険の加入者は、年齢と状況に応じて2つの区分に分けられています。
| 区分 | 年齢 | 支払い方法 | 保険料の特徴 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 原則年金から天引き | 所得段階別、自治体ごとに決定 |
| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 健康保険料に上乗せ | 勤務先や協会けんぽ経由で一括徴収 |
第1号は65歳から、年金受給者を中心に自治体単位での支払い。第2号は40歳から企業の健康保険や共済組合を通じて納付します。これにより幅広い年齢層から均等に保険料を集めることが可能です。
介護保険料は年齢別支払い義務と終了条件 – 65歳以上、70歳以上の変化や特例を含む
介護保険料の支払いは、原則40歳で開始し、その後年齢ごとかつ条件で区切られます。
- 40歳~64歳(第2号):健康保険に付属して保険料を負担する。職場により金額が異なります。
- 65歳以上(第1号):介護保険独自の制度に切り替わり、自治体ごとに金額が設定されます。
65歳で年金支給開始と同時に、原則として年金から介護保険料が天引きされます。70歳、75歳以上になっても支払いは原則継続ですが、介護認定や障害状態など特定の条件下で軽減や免除となる場合もあります。
介護保険料は月額と年額の違い、その平均値と相場感 – 全国平均や自治体間での料金差の基礎理解
介護保険料には月額と年額という2つの見方があります。月額は毎月支払う金額、年額はそれを12カ月分合計したものです。特に65歳以上の全国平均は約6,100円(2024年度時点)ですが、これは自治体によって大きく異なります。
| 地域 | 月額平均 |
|---|---|
| 東京都 | 6,800円前後 |
| 大阪市 | 7,400円前後 |
| 福岡市 | 6,600円前後 |
| 山口県 | 5,600円前後 |
自治体ごとに人口の高齢化率や介護給付費が異なるため、保険料も幅広い設定となっています。年額では月額を12倍しますが、年度内での途中改定や所得段階による変動もあるため、納付額は個人ごとに違いがあります。
介護保険料は月額の計算方法と最新基準の詳細解説
介護保険料は第1号被保険者の介護保険料の計算方法 – 基準額×所得区分での計算式と自治体ごとの差異
介護保険料の第1号被保険者(65歳以上)は、自治体ごとに定められた基準額に、所得段階ごとの割合を掛けて算出します。負担する月額は住んでいる市区町村や所得により異なり、高齢化率や介護サービス利用の状況によって基準額も違います。
2024年度の全国平均では、おおよそ月額6,000円台後半の自治体が多いですが、実際の金額は次の表のような幅で推移しています。
| 自治体 | 月額基準額(円) | 所得段階に応じた例(円) |
|---|---|---|
| 東京都 | 7,150 | 3,500〜15,000 |
| 神戸市 | 6,630 | 2,500〜14,000 |
| 山口県 | 5,568 | 2,000〜14,000 |
多くの自治体は所得区分を12段階程度設けており、低所得世帯向けの軽減措置があります。
介護保険料は第2号被保険者の介護保険料計算 – 標準報酬月額×介護保険料率×労使折半の算出方法
第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)の介護保険料は、健康保険(協会けんぽ・組合健保など)の「標準報酬月額」に、年度ごとの介護保険料率を掛けて計算します。その半額を給与から天引き、もう半額を事業主が負担します。
| 区分 | 計算式 |
|---|---|
| 本人負担 | 標準報酬月額 × 介護保険料率 × 1/2 |
| 会社負担 | 標準報酬月額 × 介護保険料率 × 1/2 |
2024年度の協会けんぽ全国平均の料率は1.82%。標準報酬月額30万円の場合の本人負担は、30万円×1.82%×1/2=2,730円となります。会社が同額負担します。
介護保険料は月額計算シミュレーションの活用方法 – 具体的な年収・地域別事例を用いた理解促進
介護保険料の月額は、年収や居住する自治体で大きく変動します。多くの市区町村公式サイトでは、年収や所得、世帯構成を入力することで、自動計算できる「介護保険料シミュレーション」が利用できます。
シミュレーション利用の流れ
- 居住地(自治体)を選択
- 年齢・所得状況・世帯構成を入力
- 該当する所得区分や保険料額を自動計算
例えば、年収200万円の単身65歳以上の方(神戸市在住)は軽減措置が適用され、月額3,000円台になることも。高所得者や二人世帯では、1万円を超える場合もあります。シミュレーションの活用で自分の負担を事前に確認できます。
介護保険料は無職・年金収入者の介護保険料計算上のポイント – 収入が一定でない場合の計算注意点
無職や年金収入のみの方でも、原則65歳以上であれば介護保険料の納付対象となります。保険料は前年の所得や公的年金収入額に基づき、所得区分表により算出されます。公的年金のみで低収入の場合、多くの自治体で最も低い所得段階が適用され、月額負担も少なくなります。
年金受給額が年額18万円以上なら、介護保険料は原則「年金天引き(特別徴収)」となります。年金が18万円未満や他収入がない場合、直接納付(普通徴収)となるケースがあります。自分の収入状況と納付方法を確認し、負担軽減制度や申請方法も把握しておくことが大切です。
介護保険料は自治体別の月額表と地域差の詳細比較
介護保険料は主要都市の月額水準比較 – 神戸市、横浜市、大阪市、福岡市などの自治体別料金差
地域によって介護保険料の月額には大きな違いがあります。特に65歳以上の方が支払う標準的な保険料は、自治体ごとに大きく異なり、都市部と地方では差額が顕著です。2024年度のデータでは以下のような比較が見られます。
| 自治体名 | 月額基準額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 神戸市 | 6,778 | 年収や所得区分で細分化 |
| 横浜市 | 6,700 | 所得段階による調整あり |
| 大阪市 | 7,486 | 都市部で全国最高水準 |
| 福岡市 | 6,400 | 比較的標準的な水準 |
| 仙台市 | 6,600 | 全国平均と同等水準 |
このように、大阪市は全国の中でも特に月額基準額が高く、都市ごとによる財政負担の違いが表れています。所得水準や地域の高齢化率も影響します。
介護保険料は地域差が生まれる背景要因とは – 高齢化率、介護サービス利用状況など制度財政面からの要因分析
介護保険料の地域差は、主に以下の要因で生まれています。
-
高齢化率の違い
高齢人口が多い地域ほど介護サービスの利用割合が高くなり、負担が増加します。
-
介護サービスの利用状況
サービスの利用者数や重度の要介護者の割合によっても、自治体の財政支出が変化します。
-
地域別の保険料算出方式
各自治体が独自に定める基準や累進段階の設定により、負担水準にも格差が生じます。
-
過去の保険料収支や国からの交付金の違い
これらが収入減となり保険料額に反映されます。
このような要因が複合して、自治体間での保険料月額に大きな差が生じています。
介護保険料は自治体ごとの減免制度や独自支援策の比較 – 減免申請条件や対象範囲の差異を具体例で紹介
介護保険料の支払いが困難な場合、多くの自治体では減免制度や独自の支援策を設けています。主な比較ポイントは下記です。
| 自治体 | 主な減免・支援策 | 対象となる条件(一例) |
|---|---|---|
| 神戸市 | 減免制度・納付猶予 | 失業や災害、生活保護受給世帯など |
| 横浜市 | 一部免除・分割納付 | 所得の著しい減少など |
| 大阪市 | 生活困窮者減免 | 前年所得一定額未満、災害時など |
| 福岡市 | 一時的な納付免除 | 失職・病気・災害被災時 |
-
主な減免条件
- 失業や大幅な所得減少
- 災害や病気による急な生活困難
- 生活保護・非課税世帯
制度によって具体的な申請条件や範囲が異なるため、居住自治体の窓口への確認が重要です。減免申請により、保険料負担を軽減できる場合があります。
介護保険料は年齢別にみる月額の実態と支払い方法の違い
介護保険料は月額65歳以上の最新相場と特徴 – 給与からの天引きから年金天引きへの変更点
65歳以上になると介護保険料の納付方法や負担額に変化が生じます。最新の全国平均月額は6,225円前後ですが、市区町村ごとに基準額や段階が設定されています。特に65歳到達時には、給与からの天引き(特別徴収)から年金からの天引きへ切り替わるケースが多くあります。なお、年金収入が一定額未満の方や年金を受け取っていない方は、納付書や口座振替による自己納付が必要になります。
| 年齢 | 月額平均 | 主な納付方法 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 6,225円 | 年金天引き、納付書、口座振替 |
保険料は「所得・世帯状況」「居住地」により段階的に金額が決まるため、必ずしも一律ではありません。
介護保険料は70歳以上、75歳以上における保険料の傾向と影響 – 老齢層の特例措置や負担感の変化を解説
70歳以上や75歳以上になると、介護・医療の両方で負担が増えやすくなります。特に75歳以上は後期高齢者医療制度の対象となり、健康保険料や介護保険料の計算方法が切り替わります。全国的に平均保険料の上昇傾向が続いており、高齢層では所得の範囲内で負担軽減措置が適用される場合があります。市区町村によっては「一定所得以下の方への減額措置」や「特定疾病による免除」も受けられます。70歳~75歳でも年金天引きが基本ですが、年金額が少ない方は個別納付を求められます。
| 年齢 | 保険料算定方法 | 減額制度の有無 |
|---|---|---|
| 70-74歳 | 介護保険独自基準 | 所得・資産による減額あり |
| 75歳以上 | 後期高齢者医療制度併用 | より手厚い減免制度 |
世帯の構成や健康状態によっても支払い負担感は変化します。
介護保険料は世帯状況別の月額の考え方 – 妻・夫との扶養関係での負担増減の実例
介護保険料は原則として個人ごとに決定されますが、世帯状況によって影響を受けます。例えば65歳以上の夫婦世帯で、夫が年金暮らし、妻が扶養の場合、妻も65歳以上であれば保険料が発生します。世帯に複数の該当者がいる場合、それぞれに課される点に注意が必要です。
-
夫婦とも65歳以上:それぞれが個別に介護保険料を負担
-
片方のみ65歳以上:その人だけが負担
-
年収や所得、世帯合算額により段階・減額も決定
高齢夫婦の場合、合算すると数千円単位で世帯全体の月額が高くなるケースが想定されます。
介護保険料は給与天引き・年金天引き・自己納付の方法別比較 – 各納付方法のメリット・注意点
介護保険料の納付方法によって利便性や管理負担が異なります。主な方法は次の通りです。
| 方法 | 主な対象 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 給与天引き | 会社員(40〜64歳) | 手間が不要、自動で納付 | 転職・退職時に確認が必要 |
| 年金天引き | 65歳以上 | 年金受給者は自動納付で安心 | 年金額によっては対象外 |
| 自己納付 | 無職・年金少額者 | 口座振替や納付書で都度管理できる | 納め忘れに注意 |
自己納付の場合は納付書の期限に注意し、口座振替の利用が推奨されます。年金天引き対象外の方は、忘れずに納めることが大切です。
介護保険料は月額と年収・職業別負担の実例と注意点
介護保険料は年収別(120万~1000万)の月額例 – 標準報酬月額からの具体的計算事例を網羅
介護保険料の月額は被保険者の年収や加入する保険制度によって異なります。会社員の場合、標準報酬月額に対する保険料率により決まります。主な計算例を下記のテーブルでまとめます。
| 年収 | 標準報酬月額例 | 月額保険料(会社員/協会けんぽ,目安) |
|---|---|---|
| 120万円 | 10万円 | 約1,670円 |
| 200万円 | 17万円 | 約2,839円 |
| 300万円 | 25万円 | 約4,175円 |
| 400万円 | 33万円 | 約5,511円 |
| 600万円 | 50万円 | 約8,350円 |
| 800万円 | 66万円 | 約11,022円 |
| 1000万円 | 83万円 | 約13,873円 |
保険料率は居住地域や年度によって変動します。また、40歳から64歳の第2号被保険者は健康保険の保険料と一緒に天引きで徴収されます。65歳以上は市町村ごとの段階別基準に従い納付額が決定されます。
リスト
-
年収が上がるほど標準報酬月額も上がり、保険料も増加する
-
納付方法は給与天引きが基本(65歳未満)、65歳以上は年金天引きまたは口座振替
-
地域や年度で料率や段階が異なるため、自治体の月額表を要確認
介護保険料は無職・年金生活者の保険料負担軽減ポイント – 所得状況により変動する計算の注意点
無職や年金受給者も介護保険の加入義務があります。特に65歳以上の第1号被保険者は、前年の所得や年金額から算出され、地方自治体が決定します。多くの自治体で所得段階別に月額が設定されており、低所得者は軽減措置が適用されやすくなっています。
一般的な軽減ポイント
-
前年の所得が少ないと最大で7割軽減も可能
-
各市区町村の「介護保険料額表」で段階と金額が確認できる
-
無職でも預貯金や不動産収入などがある場合は加味されるので注意
年金からの天引きが一般的ですが、年金額が月18,000円未満の場合や、その他の事情により口座振替になることもあります。収入や家庭状況が変わった場合は、必ず自治体に相談しましょう。
介護保険料は特殊ケースの月額 – 配偶者の収入状況や単身世帯、共働き世帯
配偶者の収入状況や世帯構成によっても、介護保険料の月額は変動します。65歳以上の介護保険料は原則として個人ごとに算定されますが、世帯全体の所得や扶養関係が影響することもあります。
主な注意点
-
配偶者が扶養に入っていても、本人だけでなく配偶者の所得や年金も段階区分に影響
-
単身世帯は本人の収入・税状況が全ての判定基準となる
-
共働き世帯や年齢差のある夫婦は、配偶者の被保険者種別も確認が必要
保険料は所得段階に応じて個別に計算され、配偶者の所得が高い場合は軽減や非課税にならない例もあります。具体的な月額や算定基準は自治体の保険料額表や公式計算シミュレーションで確認が推奨されます。 faible
介護保険料は月額の納付・徴収制度と滞納時リスクの全解説
介護保険料は月額の納付方法一覧 – 特別徴収・普通徴収・口座引落・年金天引きの仕組み
介護保険料の月額支払い方法には複数の仕組みがあります。主な徴収方法は以下の通りです。
| 支払い方法 | 説明 |
|---|---|
| 特別徴収 | 年金から自動的に天引きされる方式(65歳以上が対象) |
| 普通徴収 | 納付書または口座振替を利用し自身で納付する方式 |
| 口座振替 | 指定口座から自動引落しで月額納付 |
| 年金天引き | 年金受給者は年6回に分けて年金から直接控除 |
多くの65歳以上の方は特別徴収(年金天引き)がメインです。年金受給が無い場合や公的年金収入が一定額未満の方は普通徴収や口座振替にて対応します。自分のライフスタイルに合った方法を選ぶことが重要です。
介護保険料は支払い遅延・滞納時に生じる影響 – 租税公課の延滞金や介護サービス制限などリスク詳細
介護保険料の納付が遅れると、さまざまなリスクがあります。
-
納期限から未納が続くと延滞金が発生します。
-
一定期間の滞納で督促状が送られます。
-
さらに長期間滞納が続くと、介護サービスの給付が利用者負担割合100%(全額自己負担)となる場合も。
介護保険料は法律上の租税公課に該当し、未納の場合には差し押さえ等の法的措置も認められています。大切な介護サービス利用に支障が出ないよう、期日通りの納付が不可欠です。
介護保険料は滞納期間別の対応策と罰則 – 1年未満から2年以上のケース別の具体対応を分類解説
納付遅延や滞納が発生した場合、期間別に異なる対応や罰則が適用されます。
| 滞納期間 | 主な対応・罰則内容 |
|---|---|
| 1年未満 | 督促状送付・延滞金の加算 |
| 1年以上2年未満 | 介護サービス利用時の負担割合が通常より高くなる(全額自己負担となることも) |
| 2年以上 | 保険給付の一時差止め、財産の差し押さえなど重い措置が科される |
収入や年金事情によって一時的に支払いが困難な方は、市区町村に早めに相談することで計画的な納付や減免制度の利用等が可能です。
介護保険料は滞納リスクへの事前対策としての軽減・猶予制度活用法
介護保険料の負担を軽減するため、各自治体ではさまざまな支援策が用意されています。
-
所得が一定額未満の場合、保険料の軽減・減免制度が利用できます。
-
災害・失業・入院など特別な事情がある場合も納付の猶予制度や分割納付の申請が可能です。
-
早めに窓口に相談し、必要な書類とともに申請手続きを行いましょう。
特に低所得世帯や急な経済的事情の変化があった場合には、軽減制度・分割納付を積極的に活用することが負担増加の予防につながります。周囲に相談できる先がない場合も市区町村の介護保険担当窓口に連絡することをおすすめします。
介護保険料は月額の減免措置・支援制度と申請プロセス
介護保険料は収入減少、災害被害、低所得者向けの主な減免条件
介護保険料の減免措置は、主に生活が厳しい方や被災した方に向けて設けられています。代表的な減免条件は下記の通りです。
-
収入が著しく減少した場合
-
自然災害などで被害を受けた場合
-
生活保護受給者や住民税非課税世帯など低所得者
-
長期にわたる入院や社会的事情で収入が途絶えた場合
収入や年収が減った際、「介護保険料 いくら払う」「いくら 年収」などのお悩みも多いですが、減免の対象かどうかは各自治体が定める基準や所得金額で判断されます。該当する場合は、早めの申請が安心につながります。
介護保険料は自治体ごとの支援・減免状況と申請窓口案内
介護保険料の支援内容や減免の判断基準は、各自治体ごとに異なります。住んでいる市区町村の自治体ホームページや相談窓口で案内されています。
介護保険料の月額表や計算表が自治体ごとに公表されているケースが多く、年齢別(65歳以上、75歳以上)、世帯状況別に支援内容が確認できます。
| 自治体例 | 窓口名 | 主な支援内容 |
|---|---|---|
| 神戸市 | 高齢福祉課 | 低所得者向け減免、災害減免 |
| 横浜市 | 介護保険課 | 所得段階別減免、申請サポート |
| 大阪市 | 保健福祉センター | 災害時減免、短期猶予など |
各自治体の公式窓口に相談すれば、直接申請方法や必要な書類について個々の状況に合わせたアドバイスがもらえます。
介護保険料は減免・猶予申請の手続き詳細 – 必要書類や申請時ポイント
介護保険料の減免や猶予を希望する場合、以下の手続きが一般的です。申請の際は漏れのない準備が重要です。
-
申請書の提出(自治体窓口で入手またはダウンロード可能)
-
本人確認書類
-
所得証明書、課税証明書または収入が減少した証拠書類
-
災害時には罹災証明書類
-
場合によっては医師の診断書や入院証明も必要
ポイントとしては、収入減少や状況変化があった事実を明確に証明できる書類を整えることです。不備や遅れがあると減免が認められないこともあるため、できるだけ早く相談し手続きを進めましょう。
介護保険料は相談窓口やオンライン支援サービス活用法
疑問や不安があれば、自治体の相談窓口やオンラインサービスの活用がおすすめです。
-
市区町村の介護保険課(電話・窓口相談)
-
自治体ホームページのQ&Aやチャットボットサービス
-
ファイナンシャルプランナーや社会保険労務士など専門家相談の案内
支払いが困難になったときは「介護保険料 いくら 年収」「無職 いくら」などの細かな不安をすぐ相談し、適切なサポートを受けることが大切です。オンラインサービスを賢く使うことで、初めての方や高齢者世帯でも安心して手続きが進められます。
介護保険料は月額の疑問を解消!よくある質問総合Q&A
介護保険料は全員が支払う?支払い免除はある?
介護保険料の支払い義務は原則として40歳以上の全国民に発生します。40歳から64歳の方は、会社員なら給与天引きとなり、自営業や無職の方は国民健康保険に上乗せして納付します。65歳以上は年金天引きが主流ですが、年金額が一定以下の場合は納付書や口座振替で支払います。なお、生活保護受給者や所得の著しく低い人には減免措置や支払い免除が適用されるケースがあり、自治体へ相談すると詳細な案内が受けられます。
介護保険料は年金未受給・無職の65歳以上の負担はどうなる?
年金を受給していない、あるいは無職の65歳以上の方でも介護保険料の納付義務はあります。年金からの天引き(特別徴収)ができない場合、自治体から送付される納付書や口座振替による支払いとなります。所得が極めて低い場合、自治体によっては段階的な減免制度や納付猶予制度が用意されています。地域ごとに減免基準や手続き方法が異なるため、必ず在住する自治体の窓口で確認することが重要です。
介護保険料は年収に左右されるのか?
65歳以上の介護保険料は、各市区町村ごとに設定された所得段階によって決まります。段階は多くの自治体で9段階以上に分かれており、前年の所得金額や課税状況、扶養状況が判定の材料となります。所得が増えると該当段階が上がり、月額保険料が高くなります。以下の表は一例です。
| 所得段階 | 目安となる所得 | 月額保険料(円) |
|---|---|---|
| 最低段階 | 年金のみ等 | 3,000前後 |
| 中間段階 | 年収300万円 | 5,000~6,000 |
| 最高段階 | 年収800万円以上 | 8,000超 |
所得が低い方は保険料も低く設定されていますが、高所得者になるほど負担は大きくなります。
介護保険料はシミュレーション結果との違いはなぜ生じる?
シミュレーションサイトで試算した介護保険料額と実際に通知される保険料は異なる場合があります。理由としては、
-
自治体ごとの基礎保険料率(料率)が異なる
-
本人や同居家族の課税状況によって判定区分が変動する
-
最新の条例改正や市区町村の年度ごとの改定が反映されていない
シミュレーションは目安として活用し、正式な金額は市区町村からの通知書で確認することが大切です。
介護保険料は65歳以上の保険料が高くなる理由とは?
65歳以上になると「第1号被保険者」となり、市区町村が設定した段階別の保険料が適用されます。高齢化の進展や介護サービス需要の増加により、財源確保が必要なため、保険料は上昇傾向です。特に都市部や人口の多い自治体では要介護認定を受ける方も増加し、住んでいる地域によっても月額保険料が変わります。年々、平均額も上がる傾向があり、今後も見直しや増額が続く可能性があります。
介護保険料は支払い義務終了の条件と具体例
介護保険料の支払い義務は基本的に「死亡するまで」ですが、国民健康保険や協会けんぽの加入者で65歳未満の場合は65歳の誕生日の前日まで、65歳以上は継続して納付します。75歳になった時点で後期高齢者医療制度に移行しても介護保険料の納付義務は継続されます。なお、生活保護の受給開始や国外転出時、または所得が全くない場合には減免・免除が認められるケースもあります。具体的な終了条件や手続きについては自治体に必ずお問い合わせください。
介護保険料は公式統計・公的データの活用による信頼できる情報提供
介護保険料は厚生労働省および自治体の統計資料を基にした最新データ掲載
介護保険料の月額は、毎年度の制度改定と統計データにより変動します。厚生労働省が公表する全国平均値によると、2024年度の65歳以上の介護保険料は全国平均で6,225円となっています。都道府県ごとに保険料は異なり、例えば神戸市や大阪市など都市部は高め、山口県や鳥取県は比較的低水準です。各自治体の公式ページでも最新の月額表が定期的に公開されており、信頼できる情報源となっています。
以下の表は、代表的な自治体の2024年度65歳以上介護保険料月額の比較例です。
| 地域 | 月額保険料(円) |
|---|---|
| 全国平均 | 6,225 |
| 神戸市 | 6,800 |
| 横浜市 | 6,700 |
| 大阪市 | 7,486 |
| 山口市 | 5,568 |
最新データを確認することで、ご自身やご家族の負担目安が正確に把握できます。
介護保険料は保険料率、基準額、平均月額の推移をグラフ・表で示す
介護保険料は、年齢・所得段階・地域によって金額が異なります。特に65歳以上は「第1号被保険者」として自治体ごとに基準額が設定されています。所得に応じて段階別に保険料が決定し、住民税非課税者や年金のみの方も軽減措置があります。
2021〜2024年度の全国平均の推移:
| 年度 | 全国平均月額(円) |
|---|---|
| 2021 | 5,869 |
| 2022 | 6,018 |
| 2023 | 6,150 |
| 2024 | 6,225 |
このように、年々わずかずつ上昇傾向が続いています。所得段階や自治体の制度により、個別の負担はさらに細かく分かれます。
-
65歳以上は原則年金からの特別徴収(天引き)
-
現役並み所得は高い段階、低所得者は大幅に軽減
-
会社員や協会けんぽ加入者は給与天引きによる納付
介護保険料は専門家・監修者コメント等の引用による記事の根拠強化
介護保険制度に詳しい社会保険労務士の見解によれば、「介護保険料は高齢化や要介護認定者数の増加により、今後も基準額の見直しや地域間格差が大きくなる傾向です」。また、自治体ごとの軽減措置や相談窓口を活用することが負担軽減の第一歩とされています。
迷った場合は、自治体に設置された保険相談窓口や、医療・福祉の専門職による無料相談を積極的に利用ください。自分の収入や世帯状況に合わせて最適な支払い方法や控除制度を確認することも重要です。
全国共通で公的データと専門家の意見を参考にすることで、介護保険料の理解がより正確になります。